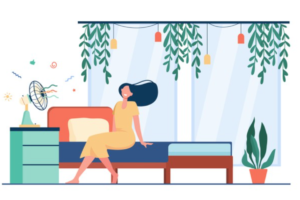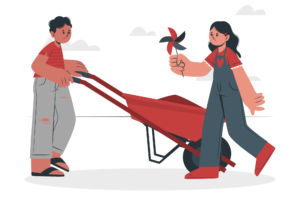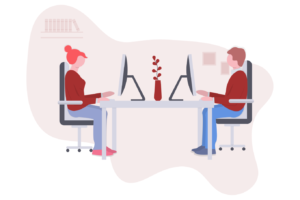普段の生活で、意識されることの多い「健康」。
その健康にも、格差が生まれていることを知っていますか?
実は、私たち1人1人を取り巻く環境によって、病気の発症率や死亡率などが違っているのです。
この記事では、健康格差の原因や日本の現状、私たち1人1人が取り組めることを解説していきます。

日本ではどのような格差があるのか、一緒に見ていこう!
Contents
健康格差とは?

健康格差とは、社会の中で属するグループや生活環境に基づく、健康状態の差を指します。
社会の中で属するグループとは、「経済」「教育」「地域」「人種」などが関係しています。
例えば、紛争地の外国と日本では生活の質、そして基準となる健康状態は違いますよね。そこには、生活環境にどのような背景があるのかが影響しています。国内でも同じように、健康の格差は起こっています。1人1人属するグループによって、病気の発症率や死亡率が高かったりするのです。

社会の中で属するグループとは「社会経済の地位」とも言えるよ。
健康格差の原因

所得格差
所得の格差は、健康状態にも大きく影響しています。
例えば、高所得者と比べて低所得者は、死亡率が約3倍であるというデータが出ています。
低所得者は費用面から医療機関の受診を控える傾向があり、健康に影響を及ぼすことがあるのです。
教育格差
教育の水準が低いほど、健康状態が悪いというデータが出ています。
幼少期の生活水準の低さが、成人後の不健康な習慣に繋がることが明らかになっています。
しかし教育格差は、生まれ育った地域や経済的な理由によって生まれるなど、問題は複雑に絡み合っています。

健康の問題は、いろいろな要因と結びついているんだね。
人種格差
人種を理由に社会参加の機会を奪われ、健康的な生活を営めないということが現実に起こっています。
例えば、黒人やアジア人であることが就職採用で不利になり、経済的機会が剥奪されているというデータが出ています。
他にも歴史的に、人種によって住む場所を隔離されてきた背景があります。居住環境に問題があるなど、健康の格差に繋がっています。

社会全体の問題なんだね…
日本における健康格差の現状
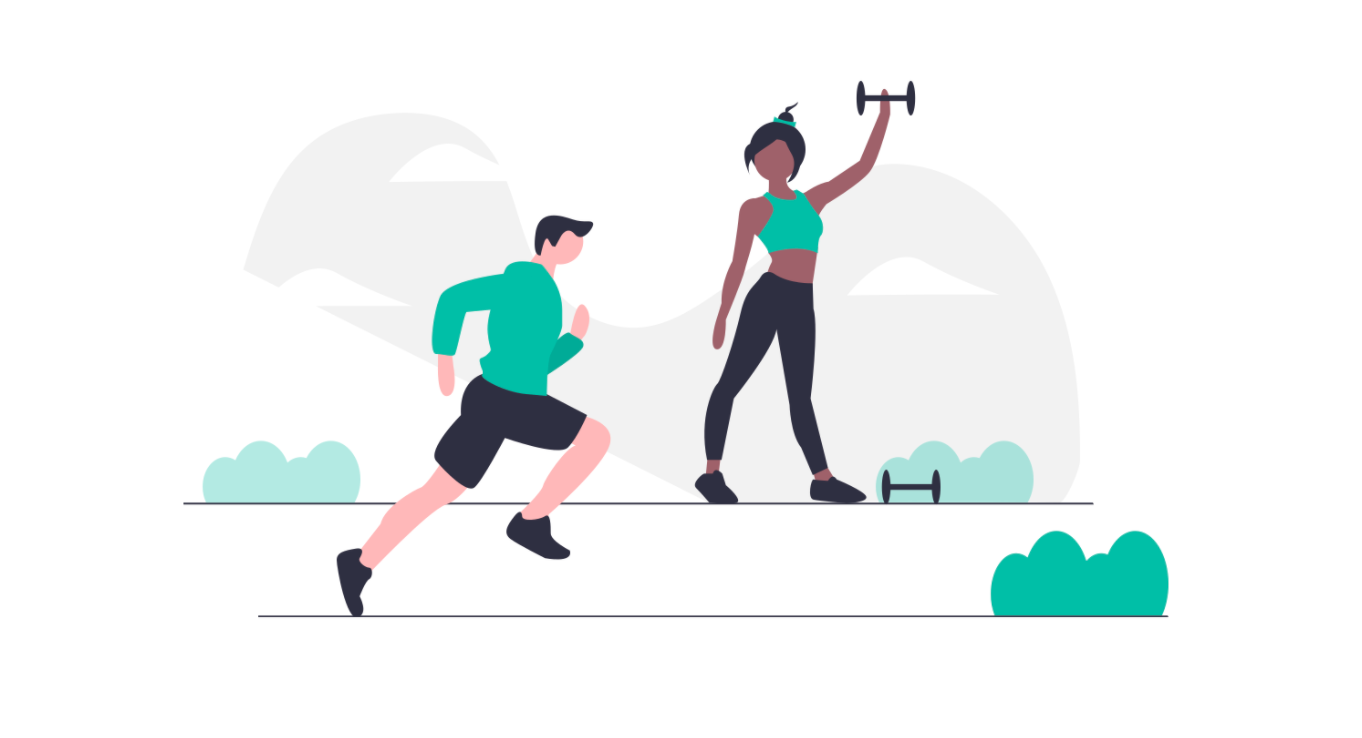
日本では1987年以降、経済格差が拡大しています。
バブル崩壊の不況により、失業率が増加したことが考えられます。特に、少子高齢化の影響で高齢者の所得格差は開いている傾向にあります。
また、正規雇用者に比べて非正規雇用者はストレスを感じる割合が高かったり、管理職・非管理職、事務作業員・肉体労働者によって脳卒中の発症率がそれぞれ異なっているというデータが出ています。これらは、身体・精神的なストレスから健康に害を及ぼしていることが原因だと考えられます。
他にも、日本人女性は家庭と仕事の両立がしにくい環境から、精神面の健康状態が低い傾向があります。これは、海外に比べて男女差が大きく、深刻な課題になっています。

経済的・社会的な格差も、健康格差に大きく関わっているんだね。
健康格差への対策や私たちにできること

健康格差への対策は具体的にどのようなものがあるのでしょうか?
例えば、地域全体で食生活の調査を行ったり、地域活動の参加を促進するなどの取り組みが行われています。このような取り組みで生活や社会環境全体の質を上げ、生活習慣病などの病気のリスクを減らすことができます。
また、貧困などの社会的に不利な人々に配慮した取り組みも必要になってきます。そして家庭環境が大きく影響する幼少期から、生活の質や環境を整える対策も行っていくことが大切です。

ぼくたち1人1人が、健康格差を縮小するための情報を知ることも解決への第1歩になりそうだね!
健康格差はすべての人に関わる社会全体の問題

身体や精神の健康格差には、社会的な立ち位置や生活環境など、複雑な要因が絡み合っています。1人1人に向けた対策だけでなく、社会全体の問題と認識しアプローチする取り組みが必要になっています。
まずは問題の実態を把握し、課題意識を持つことが重要です。
なるほどSDGsでは、こうした問題に関連したコラム記事や、SDGs達成に関わる方へのインタビュー記事をお届けしています。ぜひ関心のある記事から読んでみてください。
▼健康格差を引き起こしている貧困!日本で問題になっている「相対的貧困」とは?